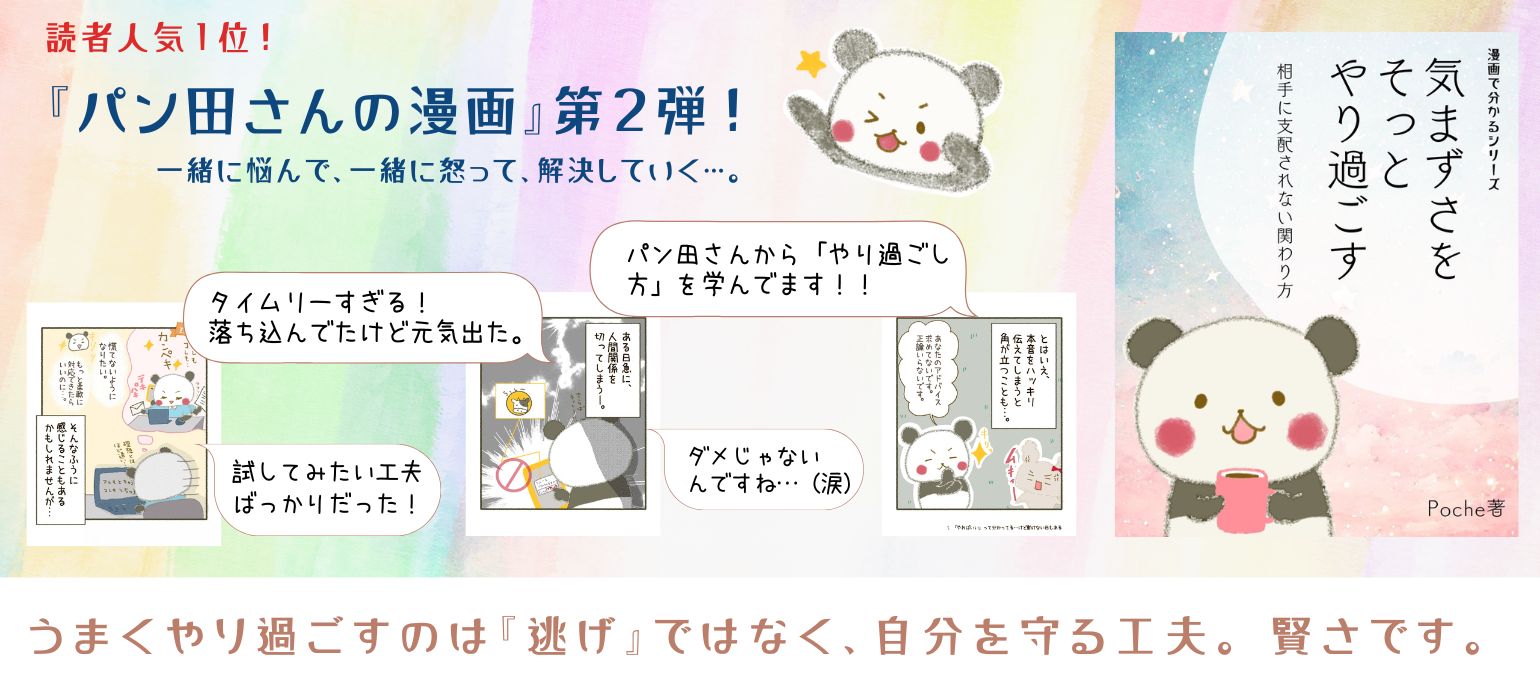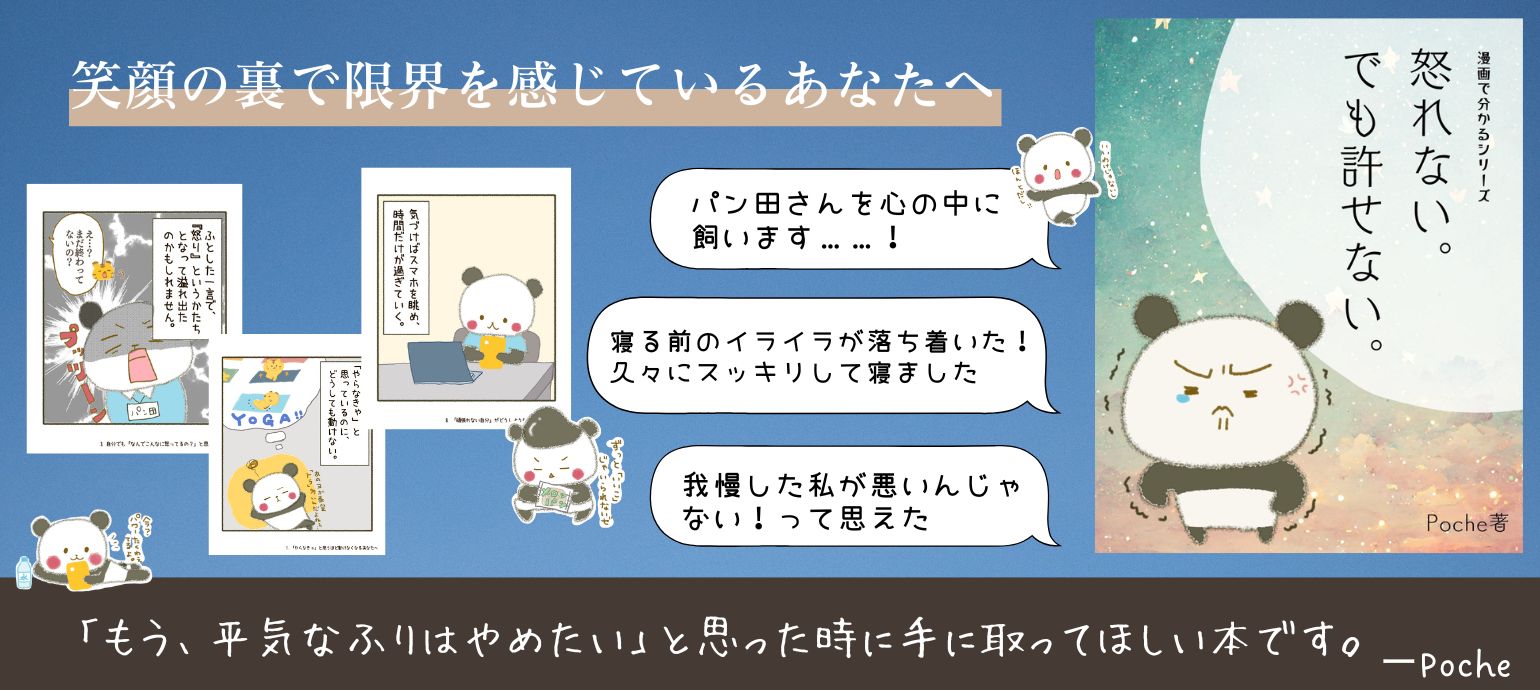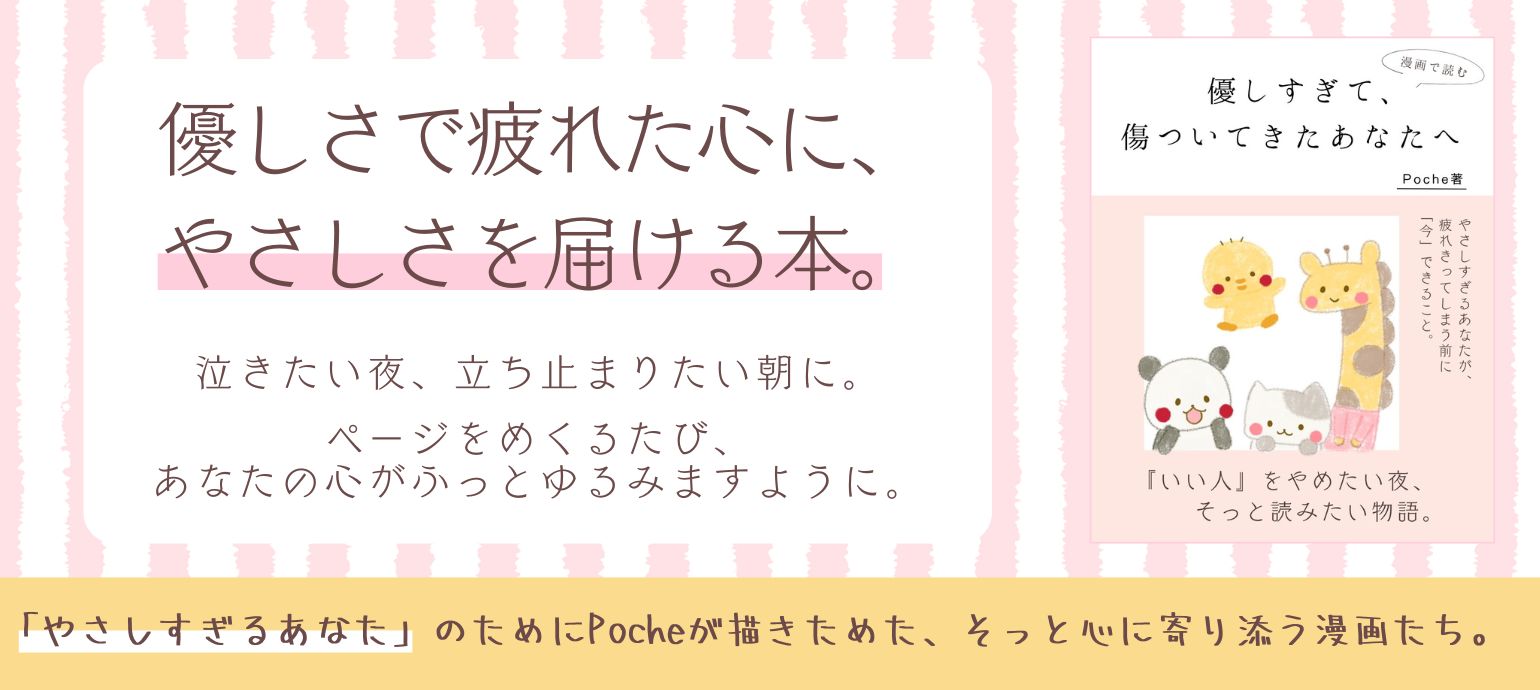人間関係がしんどい…「察しすぎ症候群」3つのサイン——気づかいが優しさを越えてしまう前に
Sponsored Links
こんにちは。
心理カウンセラーPocheです。
「きっと、こうしてほしいんだろうな」
「今、こう言ったら迷惑かな」
「空気を読まなきゃ、嫌われるかも…」
そんなふうに、人の気持ちを“察して”行動すること、ありませんか?
それは一見、とても思いやりのある行動に見えるかもしれません。
でももし…
それが「自分を後回しにしてまで」だったとしたら——
あなたの中に、気づかないうちに疲れがたまってきているかもしれません。
「察しすぎ症候群」3つのサイン

「症候群」といっても、これは病気ではなく、誰にでもある“心の癖”のようなもの。
今回は、“察しすぎ”てしまう人に見られる3つの特徴をご紹介しながら、
自分の心を守りながら人と関わっていくためのヒントを、そっとお伝えできればと思います。
特徴1:相手の顔色を見て、先回りしてしまう
誰かと話しているとき、「あ、今この話はまずかったかな」「この言い方で大丈夫だったかな」と、自分の言動を何度も振り返っていませんか?
こうした“先回りの気づかい”は、もともとの感受性の強さや優しさから来るものです。
でも…
それが過度になると、「自分の素直な気持ち」がどんどん見えにくくなってしまいます。
これから試せること
「私は、今どう感じた?」と自分の気持ちにも目を向ける習慣を持つことで、心が少し落ち着きます。
つい相手にばかり意識が向いてしまうと、自分の感情に気づけなくなりがちです。
小さな気づきを積み重ねていくことで、「自分の本音」に少しずつ優しくなっていけます。
特徴2:「察すること=正解」と思い込みやすい
「気づいてあげることが思いやり」
「わざわざ言わなくても、分かってあげなきゃ」
——そんなふうに、察することが“当然のマナー”のように思えてくることがあります。これは過去の生い立ち、家庭環境が影響しやすい部分です。
※詳細については電子書籍『漫画版:親を大切にしたい、でも〜』にてお伝えしています。
でも本当は、
察することは義務ではありません。
その優しさは素敵なものですが、それが「しなきゃ」「できないとダメ」に変わってしまうと、あなたを苦しめてしまいます。
相手の本音は、本人にしかわからないものだからです。
これから試せること
「分からないことは、聞いてみてもいい」と思えるだけで、少し肩の力が抜けます。
正解は相手にしかわからないからこそ、相手に確認することが「思いやり」になることもあります。
さらには、「察する相手を選ぶ」こと。
全ての人の様子を察するのではなく、「あなたに取って大切な人」に限定することで、察する疲れは軽減していけます。
特徴3:自分の気持ちは「後回し」が当たり前になっている
誰かの機嫌や状況に合わせることを優先しすぎて、「自分はどうしたいか」を感じる余裕がなくなっていませんか?
無意識に“自分より他人”が当たり前になっていると、知らず知らずのうちに心がすり減ってしまいます。
これから試せること
「今日、自分のために何か1つでもしてあげられたかな?」と、1日の中で2〜3回振り返ってみてください。
何もしてあげていないと感じたら、「自分のしたいこと」を1つしてみましょう。
「したいこと」が出てこない時は、
「したくないこと」を1つ減らしたり、「したくないこと」をした後にご褒美や楽しみを用意するのもおすすめです。
それだけで、自分との信頼関係が少しずつ育ちます。
おわりに

“察しすぎる”ことは、決して悪いことではありません。
それだけあなたが、相手のことを思いやれるやさしい心を持っているという証です。
でもそのやさしさが、自分の心を置き去りにしてしまっていたら…
ほんの少しだけ、立ち止まってみてください。
「察しすぎる優しさ」は、「自分を大切にする優しさ」と両立できます。
どうかあなたが、自分の心の声にも、そっと耳を傾けられますように。